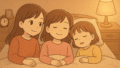【幼児の自由研究】ダンゴムシ迷路実験!家にある材料で楽しく観察できた
子どもが大好きなダンゴムシ。実は観察してみると、意外な習性がたくさんあるんです。
今回は、わが家の幼児と一緒に「ダンゴムシの迷路実験」をしてみました!
夏休みの自由研究や週末の遊びにぴったりで、家にある材料で簡単に作れるのでおすすめです。
幼児でもできる!ダンゴムシ迷路実験とは?
ダンゴムシには、壁にぶつかると左右交互に曲がる習性があります。
これは「敵から効率よく逃げるため」と考えられていて、昆虫の不思議を知る良いきっかけになります。
さらに実験の前段階として、ダンゴムシがどこにいるか探すこと自体も立派な観察です。
「落ち葉の下にいたよ!」「石の裏にかくれてる!」と幼児の発見がどんどん広がり、自然に目を向けるきっかけにもなります。
実際に幼児と一緒に迷路を作ることで、
- 工作あそび
- 観察実験
- 自由研究のまとめ
が一度に楽しめました。
ダンゴムシ迷路の作り方
材料
- 割り箸
- ストロー
- モール(針金入りのカラフルなもの)
- セロテープ
- 画用紙(迷路の土台)
すべて家にあるものでOK!お金をかけずにできます。
作り方
- 画用紙の上にストローや割り箸で道をつくる
- 分岐やカーブをつけて迷路っぽくする
- ダンゴムシをスタートに置いて観察!
幼児でも一緒に組み立てや飾りつけを楽しめました。
幼児が観察して分かったこと
- 左右交互に進む
幼児でも「こっち!今度はあっち!」と声を上げるほど分かりやすい習性。 - 壁を乗り越えた
割り箸の壁をスイスイ登る姿に、子どもは大興奮! - ストローのトンネルを通った
狭い道を選んで進むことが多く、幼児も「暗いの好きなのかな?」と気づきました。 - 方向転換で丸まる
ストローの曲がり角で一度丸まる姿を確認。敵から身を守る工夫と考えられます。 - 坂道も登れた
曲がったストローを坂にしてみると、ダンゴムシはゆっくりでも登っていきました。
幼児がまとめた自由研究の形
実験を自由研究にするときのまとめ方はこんな感じです。
- テーマ:「ダンゴムシは迷路でどう動くのか?」
- 方法:家にある材料で迷路を作り、ダンゴムシを入れて観察
- 結果:左右交互に進む、狭い道を選ぶ、坂も登れる
- 考察:敵から逃げるために工夫された動きをしている
さらに「どこにいたか探した場所」も書き加えると、観察力を評価されやすいです。
「庭の落ち葉の下」「公園の石の裏」など、見つけた場所と数を記録するだけで立派な研究になります。
幼児が描いたイラストや絵日記風にまとめても、とても可愛く仕上がります。
まとめ
幼児と一緒に楽しめる「ダンゴムシ迷路実験」は、工作と観察が同時にできる最高の自由研究でした。
- 家にある材料で簡単
- 幼児でも一緒に取り組める
- ダンゴムシを探すこと自体が観察になる
- 意外な習性を実験で確認できる
お金をかけずに親子で楽しめて、しかも夏休みの宿題対策にもなるのでおすすめです。
👉 幼児と一緒に「ダンゴムシ迷路実験」、ぜひご家庭でも挑戦してみてくださいね!